
世界で一番長い曲はジェム・ファイナーの『ロングプレイヤー』だった?
世界で一番長い曲は、ジェム・ファイナー(Jem Finer)の『ロングプレイヤー(Longplayer)』です。曲の長さは1,000年で、イギリスのロンドンにあるスタジアム、「The O2」において、2000年1月1日からコンピュータによって演奏されており、予定では反復なしで2999年12月31日まで続き、始めに戻ることになっています。
面白くてためになる雑学から、知っていても何の役にも立たないトリビアまで、幅広く発信していくサイトです。

世界で一番長い曲は、ジェム・ファイナー(Jem Finer)の『ロングプレイヤー(Longplayer)』です。曲の長さは1,000年で、イギリスのロンドンにあるスタジアム、「The O2」において、2000年1月1日からコンピュータによって演奏されており、予定では反復なしで2999年12月31日まで続き、始めに戻ることになっています。
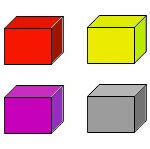
「重さ」の感覚は、色のイメージによっても左右されます。明るい色ほど軽く、暗い色ほど重く感じられるのです。具体的には、同じ重さの黒いカバンと白いカバンとでは、黒いカバンの方が1.87倍重く感じられ、疲労感も増します。1.87倍ということは、100kgの物は187kgに感じられるということで、これは例えば物を運ぶ作業に従事する人にとっては、無視できない、大きな違いとなります。

映画スターといえば、フランスかアメリカが発祥地だと思いきや、実は、映画史上に残る固有のファンを獲得した最初の映画スターは、ヘニー・ポーテン(Henny Porten、1890- 1960)というドイツの女優でした。1909年、ヘニー・ポーテン自身の脚本と主演で、ドイツの映画会社メスター社が制作した作品が大成功を収めました。この映画があまりに好評だったので、メスター社はこの女優であるポーテン嬢を実名で公開してしまったのです。
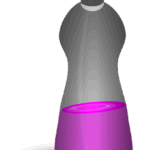
合成洗剤は、第一次世界大戦の産物だったということをご存じですか? 合成洗剤は第一次世界大戦の産物だった 戦争というと、良いイメー...
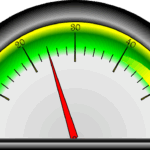
体温を計るなら体温計、お風呂のお湯の温度を計るなら湯温計というように、ものの温度を計るにはそれに適した温度計があります。しかし、数100度、或いは1000度を越える、ガラスや鉄も溶けてしまうような高温は、普通の温度計を使うわけにはいきません。そこで、現在使用されているのが「高温計」と呼ばれる特殊な温度計です。